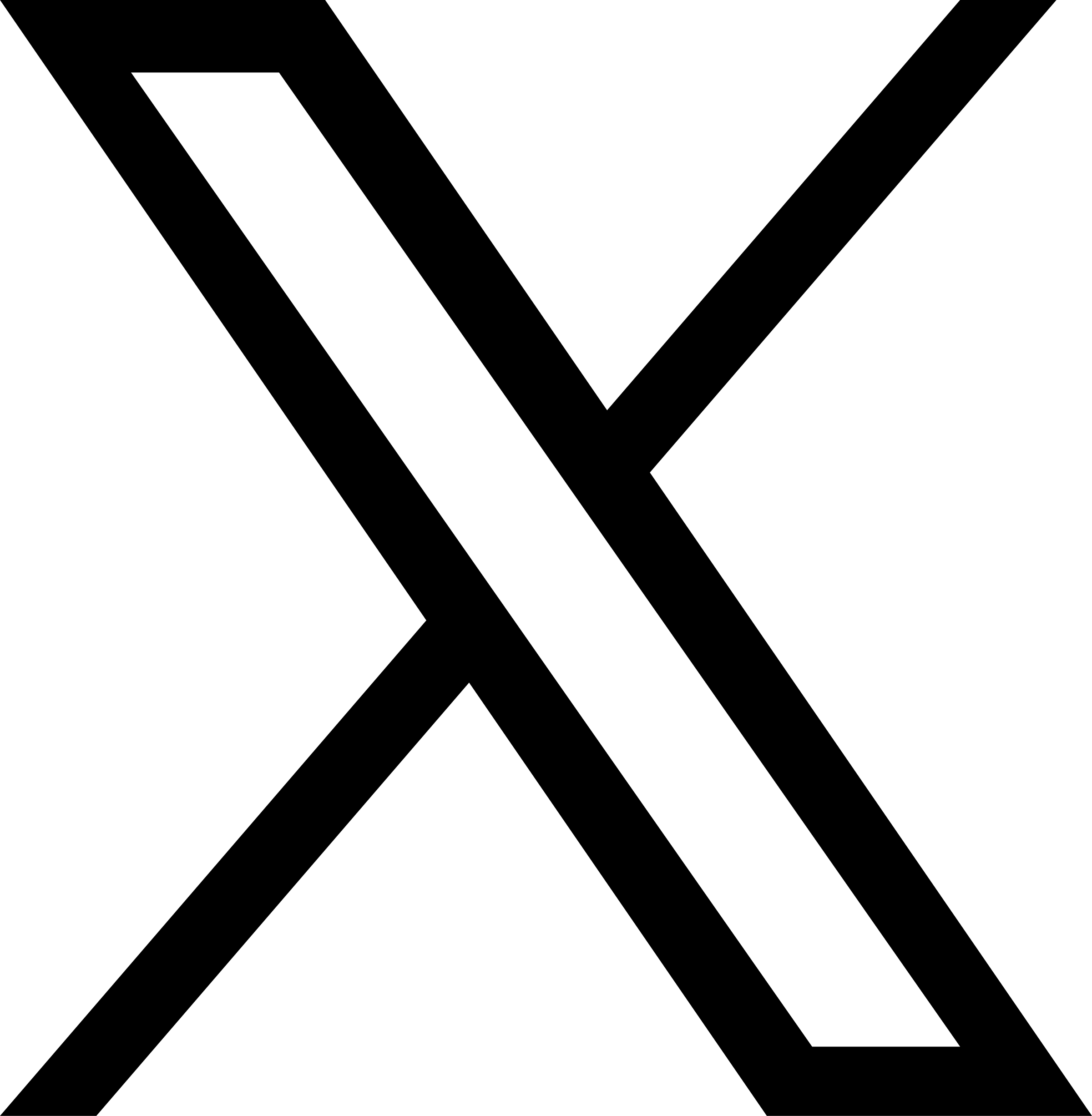消費者庁の審議会スタート
社会的受容性にかかわる定義・名称どうする?
新しい年を迎え、米国では20日にドナルド・トランプ大統領が就任し、新政権が始動しました。矢継ぎ早に大統領令を発し、パリ条約も想定通り脱退。ライフサイエンス系の政策の行方が気になるところです。ただ、「ワクチンに対して自閉症を引き起こす」など、非科学的な持論を展開して新型コロナウイルス禍でワクチン反対姿勢を貫いていたロバート・F・ケネディ・ジュニア氏が保健福祉省長官に就任すると、一転ワクチン反対論者の立場を否定しました。関係者にとってはささやかな朗報といえるでしょう。
一方、日本では1月24日に通常国会が開かれ、石破茂首相(以下、石破さん)が就任後初めての施政方針演説に臨みました。その中で、注目したいのは、地方のスタートアップ企業を支援する考えを示したことです。日本の細胞性食品の開発もスタートアップの取り組みが見受けられます。今回は、日本でも国によって細胞性食品の議論が本格的に始まりましたので、その現状をまとめます。

石破さんが地方のスタートアップ企業支援
まずは、石破さんがスタートアップを支援する真意を探ってみましょう。石破さんは看板政策として地方創生を掲げています。「地方創生2.0」として地方創生を令和の日本列島改造と位置付け、強力に進めるというのです。官民が連携して地域の拠点をつくり、地域の持つ潜在力を最大限引き出し、日本全体の活力を取り戻すべく、支援を進める構想です。そして、それは単なる資金援助にとどまらないものだともいいます。
京都府宮津市のリージョナルフィッシュは京都大学発のスタートアップ企業。ゲノム編集技術を使って成長の早いマダイやトラフグを品種改良しています。成長速度が速いため養殖にかかる飼料代や人件費も少なくてすみ、地域の産業振興に役立つ可能性を秘めています。ふるさと納税の返礼品にも採用されるなど、地域との連携も進んでいるようです。
同社は、すでに国によって研究開発などを支援する対象企業に選出されていますが、当初は資金調達や事業を拡大させるために不可欠な地元企業との連携が大きな課題となっていました。この課題解決を担ったのは、地元の京都信用金庫です。傘下にベンチャーキャピタルを持っており、リージョナルフィッシュは2024年12月に6億円の追加投資を受けたといいます。地元企業とのマッチングで京都の料亭も紹介してもらい、ゲノム編集のマダイのプロデュースなどを一緒に手掛けました。石破さんのスタートアップ企業への支援は、こうした単なる資金提供ではない“伴走型の支援”を目指すようです。
ただ一つ気がかりなのは、こうした新開発食品の国民理解への支援です。ゲノム編集技術は国による安全性評価が済んでおり、リージョナルフィッシュのほかにも、筑波大学発のサナテックライフサイエンスがGABA成分を多く含むゲノム編集トマトを開発し、販売するなど、日本は世界に先駆けて商品化を遂げています。ところが、リージョナルフィッシュのゲノム編集トラフグについては、消費者団体が「安全性が確認されていないのにふるさと納税の返礼品にしたとはいかがなものか。撤回せよ」と宮津市に対して反対運動を展開しているのです。
科学的根拠に基づかない消費者団体による反対運動はこれまでにもありましたが、放置しておけば風評となり、国民の理解は著しく棄損されます。今後進むであろう細胞性食品の適切な普及のためにも、石破さんには国民理解への確実な支援を期待したいものです。
審議会で安全性確認のための論点整理
前置きが長くなりましたが、細胞性食品もいよいよ国が正面から取り組むことになりました。2024年11月には消費者庁で食品衛生基準審議会新開発食品調査部会がスタート。2025年1月20日には第2回として、安全性確認のための論点整理が行われました。こうした食品衛生基準行政は昨年度までは厚生労働省が担っていたのですが、今年度から消費者庁に丸ごと移管されました。というのは、コロナ禍で厚労省に過剰な負荷がかかるようになったためで、厚労省の基準づくりは公衆衛生に限定されることになりました。
1月21日の調査部会では、「細胞培養食品に係る安全性確認上の論点整理(案)」と題して、事務局から細胞性食品の4つの製造工程が示され、ハザードとチェック項目が整理されました。案に示された製造工程は、2023年にFAO/WHOが報告書で示した細胞培養食品の4つの製造工程(細胞の調達、生産工程、収穫工程、食品加工)と同じで、各工程で想定されるハザードを洗い出すところから始めています。また、事務局は昨年11月の会議において日本で細胞性食品の開発や環境整備に取り組む事業者などからヒアリングした内容も考慮したと説明しました(ヒアリングには細胞農業研究機構の吉富愛望アビガイル代表も対応しています)。
委員からは「収穫は細胞培養のプロセスの中にあるため、生産工程と収穫工程を分けることに違和感がある」という意見や「複数の工程で共通するハザードについては、工程別だけでなく横断的な議論を行って効率良く整理していってはどうか」といった意見が出され、今後の方向性も示されました。
部会の終盤、「この会議では『細胞培養食品』としているものの、この名称で本当によいのか、また定義をどう定めるか、議論すべきではないか」という意見が出てきました。
現在、定義についてはFAOが2023年に文書内で示しているものの曖昧です。また、「栄養的な観点からすると、特定のアミノ酸を多く含有することなど、栄養吸収阻害などの観点からのリスク評価で必要ではないか」という意見も出てきました。つまり、定義はハザートと密接に結びついているので、定義はしっかり決めおくべきということでしょう。
名称はいろいろあるようです。「ネイチャーフード」「アーティフィシャルフード」「クリーンフード」「インヴィトロミート」「カルチャードミート」などなど。学識者からは「『培養』という言葉は一般消費者にとって抵抗感があるようなのと、世界的議論においてcell-basedという用語を使っており、養殖魚とも区別する意味で『細胞性食品』という用語を使っている。ただ、完璧な用語はまだないでしょう」との紹介もありました。さらに、「同じ細胞性食品を指すのに、表現を変えると受容性の調査結果が違ってくる」という証言も得られました。
この学識経験者が言うように、用語一つで国民理解の成否が分かれることは、遺伝子組み換え食品で苦い経験がありました。「遺伝子」という用語が「自然に反する」「道徳に反する」というイメージを植え付け、感情的な嫌悪感を醸成してしまい、科学的な正しい説明が一切受け付けられなくなってしまったのです。反対派が海外から「海外では『フランケンフード』という用語も使われている」という用語も紹介し、一層拒絶感を引き起こしました。ゲノム編集食品では、遺伝子組み換え食品の反省もあって、開発の早期からリスクコミュニケーション活動に注力したことで、上述したリージョナルフィッシュの反対運動はあっても、酷い嫌悪感までには至っていないようです。
iPS細胞に学べ!名称戦略
名称次第で受容性の成否が決まる好例といえば、iPS細胞が挙げられるでしょう。iPS細胞は遺伝子組み換え技術を使っているものの、一般消費者のこれに対するイメージは「不治の病に苦しむ人々に希望を与える技術」です。よく知られた話ですが、山中伸弥先生はこの技術を開発して世の中に発表する際、当時流行し始めて若者に大人気となったアップル社のiPadやiPhoneから着想したといいます。iPS細胞に対して、間違っても「悪魔の技術」などと言う人はいませんし、反対運動も起こっていません。細胞性食品も、「地球の食料危機を救う希望の星」のイメージで名称をつけてほしいものです。
さて、消費者庁での議論の今後の予定として、次回は2025年2月以降に開催し、その後論点整理を行い、中間とりまとめへと進みます。日本の細胞性食品の実用化は海外の先進的な取り組みから周回遅れの様相を呈していましたが、やっと議論が緒に就いたといえるでしょう。来る4月に始まる日本国際博覧会(大阪万博)での展示、いや試食までも期待する声があるとのことです。多様性のある社会にふさわしい豊富な選択肢がそろって、そこで初めて豊かな食の未来がやってくるのだと思います。
ジャーナリスト 中野栄子
東京都出身。慶應義塾大学文学部心理学科卒。日経BP社「Biotechnology Japan」副編集長、「日経レストラン」副編集長、「FoodScience」発行責任者、日本経済新聞社「NIKKEISTYLEグルメクラブ」編集長などを経て、現在フリーで食・健康・環境分野を取材・執筆中