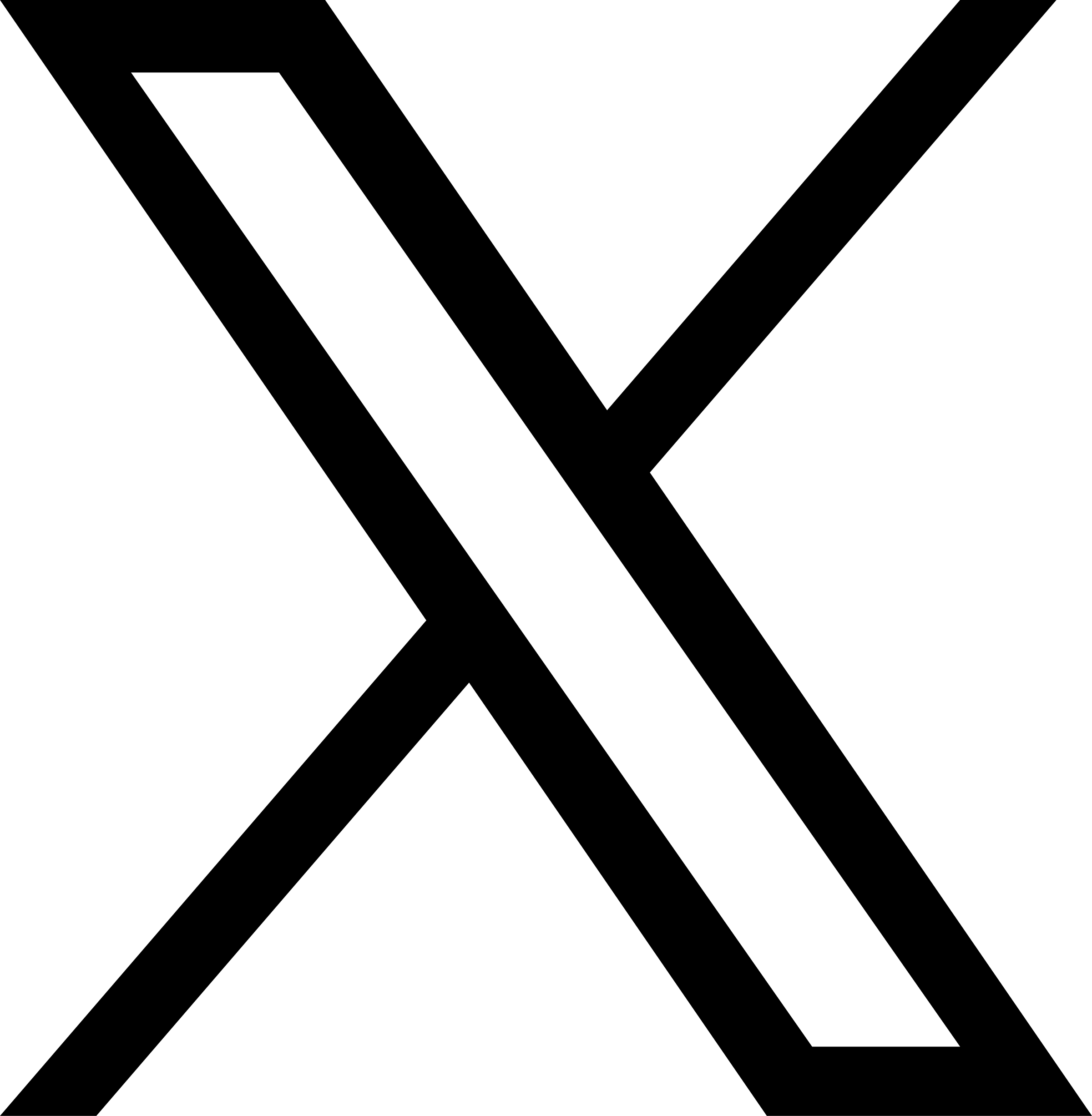中国で細胞性食品の開発・実用化に拍車
全人代の前に2つの重要文書
細胞性食品の開発・実用化に向けての世界的な動きの中で、中国の状況が徐々に明らかになってきました。政治的にも経済的にも大変気になる国であるだけに、その動きに注目が集まります。今回は中国の最新事情に迫ります。

現状、中国の規制プロセスは未整備
中国では、2021年12月発布の「第14次5カ年計画における国家農業農村科学技術発展計画」で、細胞性食品を「未来の食品製造」の1つとして促進すると言及しています。また、習近平国家主席は、植物性たんぱく質と微生物由来のたんぱく質を含む「グランド・フード・ビジョン」の策定を呼び掛けています。2025年1月には、北京市豊台区に中国初となる培養肉・微生物発酵の研究開発に特化した「中国肉食品総合研究センター新タンパク質食品科学技術イノベーション基地」が設立されました。これは首都農業発展イノベーション科学技術産業パーク内に、約8000万元(1元20円の換算で約16億円)を投じて建設されたものです。
ただ、中国ではいまだ、細胞性食品の販売を承認する規制プロセスは整っていません。そんな中、今年は実用化に向けて政府が少しずつ動き始めました。中国では毎年3月の10日間、全国人民代表大会(全人代:日本の国会に相当)と中国人民政治協商会議という政治と経済における最も重要な2つの年次総会が行われます。これをまとめて「両会」と呼ぶそうです。その両会開催に先立って、代替たんぱく質産業をさらに振興させる政府の強い意図がうかがえる2つの文書が発表されたといいます。関係者は「細胞性食品の開発・実用化に向けてのさらなる発展の兆し」と見ています。次に紹介しましょう。
1つ目の文書は、中国農業農村部(MARA)が2月14日に発表した「全国農業科技创新重点领域(2024–2028年)」という公式通知です。この通知に示された主要分野は「農産物加工と食品製造」と「農産物の品質と安全性」。前者には「新たな食料資源開発技術の研究」が含まれており、「新たなシナリオや特別なニーズを満たす新世代の食品を創造する」と記されています。後者には、代替たんぱく質やそのほかの新規資源の安全性と栄養価を評価する研究が含まれているとのこと。
いずれも、新規食品に関して明確に言及されており、代替たんぱく質の実用化につながる研究開発の増加を促すと予想されます。専門家によると、食品生産プロセスの最適化、新たなたんぱく質の配合や原材料の特定、コスト削減を可能にするマイクロバイオミクスやAIといった技術の開発に重点が置かれる見込みです。
1つ目の文書である公式通知が出された9日後の2月23日、今度は2つ目の文書「中央一号文件」が出されました。これは中国共産党中央委員会と国務院がその年最初の政策声明として発表する、農業・農村政策の方向性を示す文書です。この文書には、今年の目標として「バイオテクノロジーを活用した農業の育成・発展、新たな食料資源の探索」への取り組みを含む「多様な食料供給システムの構築」が書かれてありました。
ここには、多くの植物由来製品や発酵由来製品の開発に使用されている真菌や藻類をベースとしたたんぱく質抽出技術を含め、「食料源を拡大する」必要性について強調されていました。さらに同文書は、食の安全性と農産物の品質に対する「監視」の強化を訴えています。これは消費者からの信頼を確立し、新たなたんぱく質源を市場で調達するための重要なステップと見なされます。
この2つの文書それぞれにおいて、食の安全性が具体的に言及されているということに、細胞性食品のシンクタンクであるグッド・フード・インスティテュートAPAC(GFI APAC)のマネージング・ディレクター、ミステ・ゴスカー氏はこう訴えます。「これは、他国の規制当局への明確なメッセージです。今こそ、新規食品としての細胞性食品の開発・実用化を可能にする包括的な承認の枠組みを構築するときなのです」。
新規食品の安全性とトレサビの早期確立を
この2つの文書の発表後、「両会」でも文書の内容に沿うような発言がありました。GFI APACによると、国務院総理の李強氏は全人代の初日の演説で、バイオインダストリーを含む戦略的な新興産業のより高度な取り組みを訴えたそうです。
その延長で、中国が食品システムにおいて取り組みを強化する必要がある分野として、微生物たんぱく質の知的財産保護の強化、微細藻類などの未活用原料を活用した中国のカーボンニュートラル目標達成への貢献、国内の未来の食品関連労働力のスキルアップと育成に向けた取り組みの強化が議論されたことも明らかになりました。
最も包括的な発言は、全人代の陳魏副代表によるものでした。国が食料資源の限界を拡大し、徹底的な探査、栄養評価、代替たんぱく質の工業生産を含む資源イノベーションを推進すべきと提言したのです。さらに、国家の食料システムを向上させ、国際競争力を高めるために、新食品の「開発と応用に対する政策的保障」を強化し、この産業の人材を育成することの重要性を強調。陳氏は「ゲノム編集や合成生物学の技術は、栄養価が高く、機能性に優れた新しい食品原料の創出に役立つ可能性がある」とまとめました。
GFI APACによると、陳氏は国家衛生健康委員会と国家市場監督管理総局に対し、新規食品資源の安全性とトレーサビリティを確保するための「柔軟な規制枠組み」を構築するように要請し、できるだけ早期に統一された新規食基準を導入するという目標を強調したそうです。
代替たんぱく質の開発・実用化を推進するのは、中央政府だけではありません。省や市などの地方政府も同様の取り組みを行っています。中国とシンガポールが共同で管理する蘇州工業園区は2月、バイオ食品製造に関する2025~2027年の行動計画を発表しました。中国で最も人口の多い広東省では、植物由来、微生物由来、培養たんぱく質の技術革新を先導するためのバイオ製造拠点の建設を計画しています。
生産コスト削減に成果上げる中国企業
中国政府による細胞性食品の規制プロセス構築が現実味を帯びてくると、大学や企業の研究にも弾みがつきます。中国で初めて細胞性食肉が誕生したのは、2019年に江蘇省の南京農業大学の周光宏特任教授率いる研究チームが豚肉5グラムを製作したことに始まります。2023年には培養肉5キロの生産に成功しました。現在は、量産化に向けた研究を進めています。
中国初の細胞性食肉研究企業として2020年に創業したのはCell X 社です。細胞性の海鮮、鶏肉、牛肉などを手掛けています。2022年には、同社からアジア太平洋細胞農業協会(APAC-SCA)の事務局長が選出されています。2022年2月にはTofflon (Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd.)と戦略的パートナーシップを締結しました。シンガポールと米国の規制当局へも販売認可申請を行っており、2025年の発売を目指すといいます。生産コストを1ポンド当たり100米ドル未満まで大幅に削減しました。例えば、菌糸体製品の足場材を開発し、すでに米国で上市しています。
Joes Future Food社は、細胞性豚肉、同豚脂を手掛ける大学発ベンチャーです。南京大学の周教授の指導の下に設立されました。同社は2023年9月、世界初の細胞性豚脂肪のパイロットテストを完了しました。
極麋生物(Hangzhou Jimi Biotechnology)は、細胞性牛肉、同鶏肉を手掛ける企業です。2023年4月には中国初の細胞性鶏肉の開発に成功しています。培地のコストを1リットル当たり100元(1元20円の換算で2000円)以内に抑えることに成功し、従来のコストの3%で製造することを可能にしました。「JEVOS(Jimi Evolution System)」という、中国国内での自動化、ハイスループット化(多数のサンプルを同時に反応、処理するテスト方法)、人工知能(AI)駆動の細胞培養システムを実現したプラットフォームを立ち上げています。
今後、これらの研究開発の成否を握るのは、中国の規制プロセス構築の進展如何によるのは間違いないでしょう。それだけに、今後も中国の動向から目が離せません。
ジャーナリスト 中野栄子
東京都出身。慶應義塾大学文学部心理学科卒。日経BP社「Biotechnology Japan」副編集長、「日経レストラン」副編集長、「FoodScience」発行責任者、日本経済新聞社「NIKKEISTYLEグルメクラブ」編集長などを経て、現在フリーで食・農業・環境分野を取材・執筆中