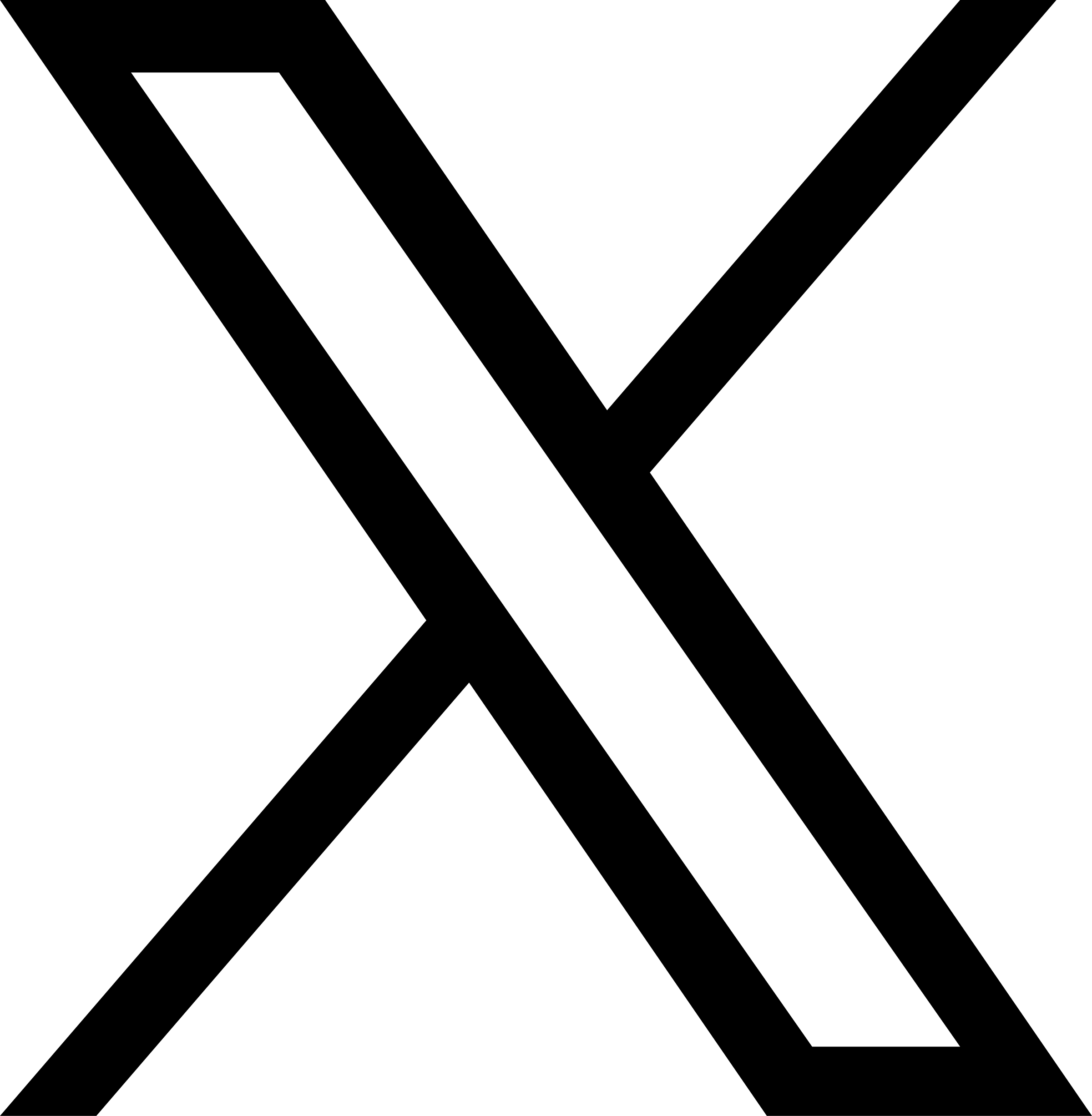なぜ「細胞性食品」と呼ぶのか
〜有識者会議にて交わされた意見を公開〜
2025年9月22日
フードテック官民協議会 細胞農業ワーキングチーム事務局
(一般社団法人細胞農業研究機構)
本リリースは、2025年6月17日に開催した有識者会議を踏まえ公表した名称方針に関する続編として位置づけています。本リリースの結論については、以下のPR TIMESに掲載された次のリリース(以下、「先のリリース」)をご参照ください。
2025年6月17日の有識者会議を踏まえ策定・公表した「細胞性食品」という名称方針について、議論の過程で交わされた具体的な意見を整理いたしました。
本続編では、特に「細胞性」という表現を支持するに至った理由や、対照的に「培養」あるいは「細胞培養」といった名称を一般報道や消費者向けコミュニケーションにおいて避けるに至った背景にあたる、実際に寄せられた有識者意見をご紹介します。
議論に参加した有識者からは、消費者の理解、既存食品との混同リスク、国際的な整合性、さらには伝統的食品産業への影響など、多様な視点から具体的な指摘がなされました。こうした意見交換の積み重ねにより、現時点で最もバランスが取れた名称として「細胞性」を採用する結論に至りました。本議論の総括につきましては、先のリリースにてご確認下さい。
【目 次】
- 各有識者のコメント表記方法について
- 各有識者の意見
- 社会科学の研究者(弘前大学 日比野 愛子教授)
- 開発研究者(東京大学 竹内 昌治教授)
- 開発研究者(大阪大学 松崎 典弥教授)
- 開発研究者、スタートアップ(東京女子医科大学 清水 達也教授、サーキュラーセルカルチャー株式会社)
- スタートアップ(ダイバースファーム株式会社 大野次郎氏)
- 水産系の食品事業会社1(開発スタートアップと連携)
- 水産系の食品事業会社2(一正蒲鉾株式会社、開発スタートアップと連携)
- 食品事業会社3(開発スタートアップと連携)
- 小売事業会社1(開発スタートアップと連携)
- 小売事業会社2(株式会社セブン&アイ・ホールディングス 矢野竜平様、開発スタートアップと連携)
- 食肉の業界の専門家(一般財団法人畜産環境整備機構 副理事長 原田英男様)
- 消費者団体関係者
- ジャーナリスト1
- ジャーナリスト2
- Good Food Institute Japan (代表 洪貴美子氏、代替たんぱく推進派国際NPO)
- 食品安全の研究者(東京農業大学 食品安全研究センター 五十君 静信センター長)
【各有識者のコメント表記方法について】
各識者の名称候補に対する立場の理解のために、下記の補助的な表記を行います。
- 下線:「細胞性食品」という名称に関するコメントのポイント
- 灰色:培養を含む名称(「培養肉」「細胞培養食品」)に関するコメントのポイント
- CF:便宜上のCell-based food もしくは Cultivated Foodの略称
【各有識者の意見】
社会科学の研究者(弘前大学 日比野 愛子教授):株式会社クロス・マーケティングのウェブベースの消費者パネル(対象人数:6,000人)に対して、2024年3月15日から3月19日にかけての4日間にかけてCFの名称に係る消費者調査を実施した。名称の優秀さの評価基準としては、Hallmanらの先行研究にて使用された評価基準を参考に次のA~Eを設定した。
- 「名称が天然魚や養殖魚、従来の畜肉等と細胞農業でできたものを区別できること」(従来品との差別化)、
- 「潜在的なアレルゲン性を示すこと」、
- 「従来品と比較して中傷的でないこと」、
- 「製品が従来品と同様の安全性と栄養価を有するという仮定と矛盾する考えやイメージ、感情を喚起しないこと」、
- 「消費者が製品を識別するのに適切な用語とみなすこと」
「細胞性」「培養」「細胞培養」に対する評定を5つの基準から分析した結果、すべてにおいて明確に優位性を持つ名称は見出すことはできなかった。「細胞性」「培養」「細胞培養」には共通点も多かったが、 それぞれの特徴も見出された(本消費者調査の報告書抜粋は後続)。名称の使用者は各名称の特徴を踏まえたうえで、名称に含める以外の方法で適宜情報を補足することが重要である。
【以下、本消費者調査の報告書(吉富・日比野、2025)(リンク先)より抜粋*】
(1)「細胞性」の使用における留意点
「細胞性」に関して、 他の名称と比較して優れる点として、第一に「魚介類」の食品カテゴリと紐づいた場合に養殖魚と混同されにくい点がある。Hallmanらの研究でも細胞性の名称を用いる方が、CFと養殖魚との弁別に役立つことが示されている。また同研究を受けてWHO/FAOによる報告書では、科学的な論文において最も使用頻度が高いのは“cultured”であったが、“cultured”は魚介類とセットで使用する場合に誤解を招く可能性がある(“may be wrongly interpreted”)として注意を呼び掛け、使用頻度の次点であった“cell-based”を専門家間の会議にて使用する際の名称として採用した。日本語では細胞培養、培養に含まれている「養」の漢字も、養殖を想起させやすいと考えられる。CFの生産者と消費者間の信頼関係構築に向けて、CFを食べたくない消費者が従来の食品であると誤認し食べてしまう可能性を避けることに重点を置くならば、この名称(「細胞性」)が適切となると考えられる。第二に「細胞性」は、他の名称と比べると「不自然である」印象を消費者に与える程度が小さい。日比野らの研究など複数の先行研究がCFへの拒絶感を強く規定する要因が「不自然さの認知」だと指摘していることを鑑みれば、少しでも不自然さや拒絶感を減らす可能性がある名称を活用することは重要である。 一方、「細胞性」を使用する場合の注意点は次の通りである。全体的な混同の程度は低いものの「培養」と同様に、植物性食品と認識される可能性はある。この点に関しては、動物細胞を培養したCFを販売する際には消費者に当該CFが「動物性」であることを明示する必要性を示唆する。加えて、強い主張は行いにくいものの、「細胞性」は他の2つの名称と比べると生産方法が明確であるという印象を与えにくい傾向があった。この名称を使用する場合は、CFが培養した細胞を原料とした食品である点や、食品の生産工程についての説明を併せて行うことが消費者への透明性担保において必要とみられる。以上をまとめると、「細胞性」は、使用している技術内容よりも、「新規性」のある食品として従来食品との誤認リスク回避を重要視する場合に、有力な選択肢となり得ると考えられる。
(2)「細胞培養」「培養」の使用における留意点
「細胞培養」を使用する場合は、分析の結果から強い主張は行いにくいものの生産に使用される技術に言及しているという利点がある。一方、馴染みのない技術用語の使用が、従来の食品との混同に繋がる可能性が示唆された。「細胞培養」の場合、魚介類の名称と紐づいた場合に回答者の半数以上が養殖であると誤認した。また強い主張は行いにくいものの、細胞性と比較すると細胞培養はCFを従来の食品と同じ香・味・食感であると思わせる程度が高かった。今回の調査ではCFを「味も見た目も調理法も同じで、同じ栄養価を持つようになる」と想定したが、実際にその想定を満たすCFが開発されるには何年もの開発が必要となる可能性がある。CFの販売にあたっては、一般消費者が想定するであろう香・味・食感や栄養素と実物の間にずれが生じないよう、販売元は説明責任を果たす必要があるだろう。「培養」は「細胞性」と「細胞培養」との中間的な位置づけにある。生産に使用される技術を想起させながらも、不自然だという認識を与えにくい利点がある。一方、養殖と混同されやすい度合が「細胞培養」よりも高いという限界がある。WHO/FAOによる報告書では、科学論文における“cultured”の使用率が最も高いことが示されている。日本国内においても学会やコンソーシアムの名称に「培養」という言葉が使用されるなど、「培養」は科学者(特に開発者)にとってその食品に使用されている技術力をアピールするうえで好まれる傾向のある名称だと考えられる。
*見やすさ向上のため、参考文献番号を削除する、下線やハイライトの追加等の微調整を行っている点にご留意ください。
開発研究者(東京大学 竹内 昌治教授):通称というよりは、食品を販売する際に、例えばペットボトルを購入した場合に「清涼飲料水」と表示されているような、それに当たるに法制度で用いる「名称」を提案するという認識である。それについては、誤認・混同がなければ基本的にどのような名称でも構わないと考えている。例えば「細胞性」「培養」「細胞培養」といった表現について、細胞性は「cell-based meat」や「cultivated meat」が欧米でも浸透してきており、それに相当する言葉として適切であると考えられる。「培養」についても、技術を正確に表す名称としては良いが、「培養」の「培」という語感にネガティブな印象があるのではないかと感じている。そのネガティブさをどの程度緩和したいかによって、議論の分かれ方も変わると考える。個人的には、「細胞性食品」がこれまで使われてきたため、そのまま進めてもよいと考えているが、特段その名称にこだわりがあるわけではない。CFの名称に関する着地点については、最終的には行政の見解を踏まえて運用する事項であると理解している。そのため、業界団体としていくつかの候補名称をサジェスチョンとして挙げておくのが適切であると考える。
開発研究者(大阪大学 松崎 典弥教授):まず名称に関して、個人的には「正確に表す」というのが大事だと考えている。現在「培養肉」と呼ばれているものが、他の食品と異なり、ガイドラインも必要とされている理由は、「細胞を使い、それを培養している」という点がこれまでにない食品であるからだと理解している。カタカナでも漢字でも構わないが、「細胞」と「培養」という言葉は入っているべきだと思う。それが正しく表現するということではないか。消費者の多くは、まだこの食品を目にしたことがないと思われる。現時点で名称を決めても、将来的に社会に広く普及すれば、また変更される可能性もあると感じている。したがって、現時点では「正しく伝える」ということが第一であると考える。着地点については、最終的にはガイドラインや法制度によって決まっていくものだと思う。現状では、ある程度の候補を挙げておくことが適切だと考える。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
松崎先生のコメントを受けて、先のリリースは、あくまでも細胞培養技術に馴染みのない一般消費者向けに従来食品との混同などの誤認を生じさせないための発信方針としました。また、専門家間での議論の際には、細胞性食品に対する誤解が発生する可能性が低いことから、技術を短く表すという意味での「正確」な名称の採用について、否定をしない主旨の文言を追加いたしました。
名称に関しては、「技術的・科学的観点での美しさで名称を選ぶことが誠実」という考えもあれば、「その技術者の主旨が消費者に伝わらない、ましてや養殖や肉と同じ品質と誤解を消費者に対して招くことで既存産業と軋轢を生むのであれば、その効果も加味した名称選びを行うべき」という考え方など様々なものがあり、どれかが一概に正しい・誤りであるというものではない理解です。先のリリースは、一般向けの発信を想定していることから、後者の考え方に沿い、技術に加え、安全・コミュニケーションの面で論点を整理した結果となります。
開発研究者、スタートアップ(東京女子医科大学 清水 達也教授、サーキュラーセルカルチャー株式会社):もともとガイドラインができる前から、こうした「培養肉」のルール形成に関わっており、最初にインテグリカルチャー社らと関わり、途中から「細胞性食品」や「セルベーストミート」という表現が使われるようになった際にはその名称を普及させるよう努めてきたつもりである。今回、改めて議論が始まり、ゼロベースで考えると、「細胞性」という言葉自体は、たしかに先日の審議会でも「意味がよくわからない」という意見があった。特に「性」の意味が不明確だと。セルベースであれば理解しやすいという声もあり、「細胞性」という言葉を使うなら、いっそ最初から横文字で「セルベース○○」とした方がよいのではないかと考えている。「培養」については、他の先生と同様、すでに我々にとっては違和感がなくなっており、実際のプロセスを明確にするという意味でも、「細胞」や「培養」といった語は入れるべきだと考えている。先日、我々は学会を立ち上げたが、その際にも名称をどうするかが議論になった。最終的にはアカデミアの場であり、かつ対象が肉だけではないことから、「培養食料学会」という名称にした。宣伝になるが、ぜひ皆さんにも加入していただきたい。この「培養食料」という語を今後使っていきたいと考えている。そのため、セルベースにこだわらないならば、むしろ「培養」という言葉を入れた方がよい。細胞という語を加えると長くなるという問題もあるので、製品表示として裏面に正確な説明を記す場合は、「培養した細胞を加工して作る食品」として、「培養細胞加工食品」とするのが最もしっくりくる。ただし、これは俗称として使うには長すぎるので、日常的には「培養肉」や「培養食料」などが適しているかもしれない。ターゲットが正式な表示ラベルであるなら、「セルベースミート」や「セルベース○○」、あるいは「培養食料」といった言葉に、意味が伝わるよう工夫すべきである。学会名としては「培養食料」を使っているが、 正式名称としては「培養細胞加工食品」とするのが望ましいと考える。俗称は「培養肉」などでよいとしても、正式な名称はきっちりしたものにした方がよい。細胞性という表現をリセットするのであれば、「培養」の語をむしろ世の中に馴染ませていく方がよいというのが率直な意見である。また、国際的には「cultivated food」という名称が使われており、我々の学会でも英語名はそれに合わせている。これはある程度、国際的な流れに歩調を合わせたものである※。一方、足並みを揃えるという点では、省庁に確認しても「誰が決めるのか分からない」という状況がある。だからこそ、今日この場に集まっているような、長年この分野に関わってきた人たちである程度方向性を決めて、むしろ省庁に提案する方がよいのではないかと考えている。少なくとも、かなり候補を絞り込んだ状態にする必要があると思っている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
現時点で100%最適といえる名称は存在しないという点を強調しつつ、一般向けのコミュニケーションにあたっては、名称のみに委ねるのではなく、それらの留意点を踏まえた丁寧な説明・補足の工夫が不可欠である前提のもと、先のリリースでは、「『細胞性』という名称の使用に関する留意点」として、ご指摘の論点を「②細胞『性』の訳語への違和感と代替語の限界」及び「③『意味がよくわからない』との初期印象の可能性」に反映しました。②では、カタカナ表記(セルベース)や補助的な説明文と併用するなど、柔軟な対応が必要であるとしました。先のリリースは、名称候補がすでに複数ある現状から、混乱を避けるべく既存の使用歴のある名称の中から一つに収束させるという主旨であったため、新しい名称の提唱はできませんでした。しかし、オフィシャルな書き言葉として「細胞性」という漢字名称を使用し、読み方としては「細胞ベース」や「セルベース」という表現を使用することもあり得ると考えられます。
また、※の点については、先のリリースで参照した世界保健機関(WHO)及び国際連合食糧農業機関(FAO)の発表した情報によると、学術論文にて最も使用されているのはcultured foodであり、次席はcell-based foodです。一方で、代替たんぱく質推進派の国際NPOのGood Food Institute はcultivated foodを推進しています。どの名称が国際標準かという考え方については、複数の考え方があります。消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として設置された国際的な政府間機関コーデックス委員会の設立母体である世界保健機関(WHO)及び国際連合食糧農業機関(FAO)が採用する名称(cell-based)を標準だとする考え方もあれば、細胞性食品分野などを推進し、業界内での認知度が高い代替たんぱく質推進NPOの提唱する名称(cultivated)を標準とする考え方もあります。
スタートアップ(ダイバースファーム株式会社 大野次郎氏):名称について、「細胞性」「培養」「細胞培養」などの案があるが、自分としては、どちらかというと消費者に受け入れられやすいことを重視すべきだと感じている。ビジネスを行う以上、最終的に購入してもらうのは消費者であり、イメージの良い名称であることが重要だ。この考えには背景がある。自分の妻が「培養」と聞いただけで「もう嫌だ」と拒絶反応を示した。培養という言葉に良い印象を持たない人は一定数いる。ある助成金に応募した際、最終選考まで進んだが、名称の印象で落とされた。審査員の一人であった30代の子育て中の女性が、「培養したものなんて子どもには絶対に食べさせたくない」と言ったのである。これは自分にとって衝撃だった。自分にとって「培養」とは清潔で前向きな技術だったが、それが必ずしも一般の人々にとってそうとは限らないということに気づかされた。やはり、一般の感覚を汲み取ったうえで名称を選ぶべきだと痛感している。そのうえで、自分としては、先生方もおっしゃっていた通り、「細胞性食品」という言葉はこれまで浸透してきた経緯があり、十分に馴染みが出てきていると感じている。また、「セルベースド」という表現は国際的にも広く使われており、「プラントベースド」との対比としても分かりやすい。したがって、「細胞性食品(セルベースドフード)」というのが最も良いのではないかと考えている。「細胞性」という語は、これまで使われてこなかった新しい言葉であるからこそ、今後フレッシュで前向きなイメージを付与していける可能性もある。最後に、名称の着地点についてであるが、我々もこれまで5年ほど培養肉や細胞性食品の開発に取り組んできた。WT事務局を起点に、業界内では多くの意見交換も行ってきた。そこで、我々民間がまず「細胞性食品」と決めて使用を始め、WT事務局および会員企業で共通名称として定着させていく。そうした動きが、やがて省庁や行政に広がっていくという流れをつくることも十分に現実的ではないかと考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
技術的用語が、技術者に与える印象と、消費者に与える印象が大きく異なる点についての例をご共有いただきました。同社は生産農家やレストランシェフと連携し、細胞性食品の開発・生産から消費者への提供までを想定されているため、企業間取引(BtoB)を想定する開発企業等とは異なる視点での意見をいただいたとの理解です。
BtoBの場合、技術のみに基づく用語を使用しても、それにより想起されるイメージが大きく異なることは考えずらいものの、BtoCを意識して社会実装を行う場合はその限りではない可能性が示唆されました。
水産系の食品事業会社1(開発スタートアップと連携):これは同社の事業者側の立場としての発言である。私は研究者ではないが、事業面から培養肉のプロジェクトに関わっている。私の意見としては、先ほどの意見と同様に、消費者がどのように受け止めるかを第一に考えるべきだと考えている。その観点から、我々もWT事務局の活動に合わせて「細胞性食品」という名称で統一して取り組んできた経緯があり、この名称に対して特に違和感はない。
また、カタカナの名称についても言及したい。日本語の名称とカタカナの名称は両方あった方がよいと考えている。カタカナだけに統一されると、「外国から入ってきた食品」という印象を与えかねず、一般消費者にとっての心理的ハードルになる恐れがある。そのため、日本語では「細胞性食品」、カタカナでは「セルベースト」といった表現の併用に対しても違和感は感じていない。
今後はWT事務局のリードのもと、足並みを揃えて消費者やメディアに対する名称の普及・認知活動を同時に進めていくことが重要だと考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
市場の形成は、細胞性食品分野における上流から下流まで、本産業に関わるすべての開発者のゴールであると考えられます。
開発者のゴールである市場形成の前線となるのは、実際の消費者への販売を担う食品事業会社や小売事業会社による消費者コミュニケーションです。また、実際の食品表示に関しても、当該のステークホルダーが担うところが大きいと考えられます。その消費者への前線での情報発信を担うステークホルダーからの意見として上記のコメントはとらえることが可能です(以下、他の食品や小売事業会社についても同様のことが言えます)。
また、上記コメントにて、WT事務局に期待される動きについての言及がございました。よって今後の取り組みとして、先のリリースにおける「今後の取組方針」として「(必要に応じて)より略称的な呼び方に係る追加的検討を実施」という内容を挙げました。
水産系の食品事業会社2(一正蒲鉾株式会社、開発スタートアップと連携):今回は消費者視点を中心に意見を共有したい。私の所属する部署は商品開発やマーケティングとも関わりが深く、そうした観点から発言する。現在提示されている三つの名称には、それぞれ長所・短所があると感じている。まず「細胞性」については、「人工」や「合成」といったネガティブな印象を避けられる反面、「医療的」なイメージを与えてしまい、消費者に抵抗感を与える可能性があるという印象を持っている。「培養」に関しては、すでにメディア等で「培養肉」という言葉が使われており、耳馴染みがある。消費者にとっても「こういうものなのかな」といった認識は徐々に形成されつつあるように思う。一方で「培養」という言葉は、「自然ではない」「不自然」といった印象を持たれる可能性がある。最後に「細胞培養」は、誤解の余地が最も少ない名称である一方で、技術寄り・専門的な印象が強く、食品としての親しみやすさや購買意欲には結びつきにくい面もあると考えている。いずれの名称を採用したとしても、一定の割合でネガティブな反応を示す消費者は必ず存在すると考えられる。そのため、そうした人々に対しては、きちんと科学的根拠をもって説明できる体制を整えておく必要がある。名称だけで信頼を得るのではなく、背景にある正確な情報の提示が重要である。最後に、現在議論している名称は、おそらく裏面表示に関わる一般名称として想定されていると思う。しかし、これらの名称は消費者とのコミュニケーションツールとしてはやや弱い印象がある。実際に店頭に並んだ際、訴求力が限定的になる可能性がある。そこで提案したいのは、WT事務局などが主導する形で、名称とは別のかたちでレギュレーションを整備し、認証マークのような“別のコミュニケーションツール” を導入することである。そうすることで、消費者との心理的な距離を縮める手段になり得ると考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
先行して実施した消費者調査では、明確に「医療的という印象をもつか」という側面で調査参加者への質問を設計しなかったため、この点については検証が不十分な状態です。
「きちんと科学的根拠をもって説明できる体制を整えておく必要がある。名称だけで信頼を得るのではなく、背景にある正確な情報の提示が重要である。」という点はまさにご指摘の通りです。先のリリースでは「現時点で100%最適といえる名称は存在しない」点を強調しつつ、「一般向けのコミュニケーションにあたっては、名称のみに委ねるのではなく、それらの留意点を踏まえた丁寧な説明・補足の工夫が不可欠です。」という文言を含めました。
上記コメントにて、WT事務局に期待される動きについての言及がございました。よって先のリリースにおける「今後の取組方針」として、「(国内の上市について目途が立ち次第)販売事業者との連携による、ラベル/表示に係る自主ルールの検討と策定、認証マークや規格化に係る検討」という内容を挙げました。
食品事業会社3(開発スタートアップと連携):まず、政府による名称の決定に関してであるが、消費者が理解できる一般的な名称が望ましいと考える。また、「食品」であると認識できる用語を用いることも重要である。たとえば、「培養」や「ラボ」といった、化学品を想起させる用語は避けるべきだと考えている。さらに、CFを特別に優れたものであるかのようにアピールする名称も避けるべきだと考える。現物食品に対する優良誤認のような誤解を与えることは避けたい。今回の議論はオフィシャルな表示名称に関するものではないと事前に伺っているが、表示の観点からも一点指摘したい。原材料名欄の表示について、食品添加物のように表示されること、例えばスラッシュ(「/」)後への表示は避けたい。今後の着地点について述べると、一度望ましくない名称や印象が社会に定着してしまうと、それを修正するのは非常に困難である。私どももこれまでにそのような経験をしてきた。そのような観点からも、業界として早い段階から望ましい名称を使い始めることが重要だと考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
「CFを特別に優れたものであるかのようにアピールする名称も避けるべき」や「現物食品に対する優良誤認のような誤解を与えることは避けたい」という観点について、先行の消費者調査では、効果量を考慮しない場合(すなわち、強く主張できるわけではないものの)、「細胞培養」は細胞性と比較して従来の食品との同質性(同じ味・触感・香り等)を印象付けやすい可能性が示唆されました。そのため、畜産業界等への配慮から、「細胞培養」という名称の使用を避けることは一案であると思料されます。
また、過去に事務局にて技術に馴染みのない方々向けに講演会などで情報発信を行った際には、「塊肉を2倍、4倍にする技術か」「サーロインの細胞を培養するとサーロインの塊に育つか」等の質問がありました。科学的な検証は行っていないものの、「培養」という用語によって、キノコの培養生産のように、「肉を塊のまま2倍、4倍に増やしていく」というイメージを持たれる方は一定数いらっしゃる可能性があります。この第一印象によって、従来の食品生産を「脅かす」イメージを「培養」という用語が想起させる可能性が考えられます。
小売事業会社1(開発スタートアップと連携):私は自社で商品の販売を担当しており、CVCを通じてスタートアップなどに投資している。また、フードテック官民協議会において「プラントベース・ライフスタイル・ラボ」の技術検討会に関与しており、プラントベース商品の表示ルールや、先日発表した認証制度の策定にも関与している。今回はそうした経験を踏まえて意見を述べたい。まず、名称に関する考え方として、「消費者にネガティブに思われない」ことを目的にするのではなく、選ばれるためにはどうすべきかという視点、つまり「マーケットイン」の発想が必要だと考えている。たとえば、弊社はプロダクトアウトではなくマーケットインでネーミングを行っており、培養肉に関しても同様の考え方を採用すべきである。当社があるスタートアップに投資を決めた際には、CFという分野に対する懸念もあったが、株主や顧客からはむしろ好意的な反応が多かった。「将来性があり、早い段階で関与することは良い判断だ」という意見が多く寄せられた。当社は比較的安全性を重視する会社だと見られていると思うが、それでも問題はなかった。逆に、アニマルベースに対する倫理的懸念から、それを避けたいという声も一定数あった。したがって、過度に“気持ち悪い”などの否定的な印象を恐れる必要はないと考えている。名称に関しては、英語の“セルベース(cell-based)”が良いと考えており、日本語では「細胞性食品」が適していると感じている。理由は以下のとおりである:国際的な一般表示との整合性があること。業界内(特にスタートアップ関係者)でも“セルベース”の表現が広く使われており、最も自然な選択肢であると感じること。新しい分野では、英語名称がそのまま定着する例が多く(例:スマホ、フードテック)、“セルベース”も同様に受け入れられると考えられること。なお、5年前にフードテックという言葉が日本にまだなかった頃、大臣が日本語にしようと「新規性食品」などの案を出したが、今では「フードテック」が定着している。新しい言葉は、使っていくうちに自然に浸透していくものである。プラントベース食品に関しては、プラントベースの領域については、私が関与しているもう一つのフードテック官民協議会で、認証制度を作成したところから、かなり違和感なく使われるようになった。食品表示のガイドラインや認証制度で「プラントベース食品」と命名し、発表したことで定着してきた。言葉は使っていくことが重要であり、「難しい」や「浸透しない」といったことはないと考えている。プラントベースに関しても、当初メディアや消費者から「長い」「英語は嫌だ」と言われていたが、今では十分に落ち着いてきたと感じている。したがって、「プラントベース」「アニマルベース」「セルベース」といった分類で、消費者が選択できる構造をつくることが適切であり、セルベースが良い選択肢だと考えている。最後に着地点について述べると、認証制度はプラントベースの時の成功事例であった。セルベースについても、JASや協会などで認証マークをつけることで、定着が進むと考えている。一方で、プラントベースの表示について一つだけ後悔していることがある。裏面表示の際に、原材料に「プラントベース肉」と書けるかどうかという点で交渉を重ねたが、結果として書けず、「脱脂大豆」などの表記になった。このようになると、消費者には何が入っているのか分かりづらくなる。したがって、CFに関してはこの部分は譲らずに対応するべきであり、今後のWT事務局の交渉にも期待している。プラントベース食品のガイドラインにおいては、「肉」という表現を使ってもよいという整理になっている。和牛などは商標の問題があるため使えないが、「肉」が使えないわけではない。この点も整理して運用していけばよいと考えている。また、アレルギー表示についても、別途「○○を含む」といった表示が必要となるため、「肉」という言葉が入っていなくても消費者には情報が伝わる。最後に余談になるが、消費者目線で名称を決める際には、選んでもらうための価値をどう伝えるかが重要である。たとえば「クリーンミート」のように、価値を訴える言葉が本当は望ましい。ただ、現時点では海外でも「セルベース」という表現が主流であり、製造方法を伝えることが基本であると考えている。「プラントベース=植物由来」、「アニマルベース=動物由来」、「セルベース=細胞由来」といったように、由来が明確になる構造で分類されることが重要であると考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
「マーケットイン」の発想が必要という点はまさにおっしゃる通りです。一方で消費者にとっての価値については、開発途中の細胞性食品が多く、現時点で期待されている機能を実際にはどこまで実現できるかという観点の検証が必要となってくる理解です。また、その検証が現実的に可能となるには、実際の製品の上市が近づいた2-3年後などになる可能性があります。では今後も上市環境が整うまでの数年間、皆思い思いの名称を使ってもよいかというと、そうでもない理解です。本議論を実行するに至った背景にもなりますが、メディア関係者より名称に複数候補があり困っている、国際NPOより名称統一の議論が必要であるという声が挙がっていたためです。
「細胞性」は必ずしもマーケットインではないものの、「プラントベース」との対比で「セルベース」といった分類が分かりやすいという発想は、事務局としては違和感なく感じられました。また、「『プラントベース』『アニマルベース』『セルベース』といった分類で、消費者が選択できる構造をつくることが適切」という点は今後の消費者向けの発信において参考となるほか、「JASや協会などで認証マークをつける」という点についても、WT事務局として連携可能な事業会社を探し、事例づくりを進める余地があると思われます。
また食品表示のその他の観点については、WT事務局にて情報整理を行った結果を2025年8月にWT会員向けに共有を行っております。
小売事業会社2(株式会社セブン&アイ・ホールディングス 矢野竜平様、開発スタートアップと連携):開発戦略部に所属し、実際の商品開発を担当している。本日私がお話ししたいのは、「お客様の視点」でこの問題をどう考えるかという点である。いわゆる「顧客起点」とも言われるが、その観点から述べたい。まず、「細胞性」という言葉については、あまり負のイメージを持たれることは少なく、大半の方にとって問題ないと感じている。したがって、「細胞性食品」に関しては“丸”を付けられると考えている。次に「培養」については、多くの方がネガティブな、つまり負のイメージを抱いてしまうのではないかと危惧している。三つ目の「細胞培養」に関しても、「細胞」という語自体には問題がないと思われるが、「培養」という語が含まれることによって、やはり消費者に負の印象を与えてしまう可能性が高いと考えている。ここで重要なのは、一度消費者に負のイメージを持たれてしまうと、それを払拭して“ゼロ”に戻すだけでも相当な労力が必要になるという点である。さらにそこからプラスのイメージに転換しようとすることは、至難の業とも言えるほどの努力を要する。そのため、そもそも負のイメージを与えないことが極めて重要であると考える。本日参加している皆様に共通しているのは、この新しい技術が消費者に安全性も含めて受け入れられ、さらに社会に広く普及していくことが共通の目的であるという認識である。その前提に立つと、持続可能性の観点からサステナブルな調達を推進していく上でも、消費者に負の印象を与えない名称を選ぶべきだと考えている。その点で言えば、「細胞性」が“丸”ならば、「セルベース」は“花丸”をつけたいほど評価している。負のイメージを持たれることなく、消費者に受け入れられていく可能性が高い名称であると考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
今回は、名称の混乱を避けるべく、使用歴のあるものを中心に検討するという設計で議論を行いましたが、一方で「セルベース」という名称に対して、食品や小売の事業会社より一定の支持がある点については今後より深堀をしてまいりたいと思います。よって先のリリースにおける「今後の取組方針」として、「(必要に応じて)より略称的な呼び方に係る追加的検討を実施」を含めました。おそらく、漢字での名称も必要となるため、日本語の名称としては「細胞性」を採用しつつ、その読み方や略称として「セルベース」を併記する形になる可能性もあると考えております。
事務局といたしましては、事務局自身が細胞性食品を取り扱う事業会社でないことから、特に使用歴のない新規名称を略称として業界へ提案する場合、事務局のみで音頭をとるよりも、実際に広報・対外発信などで積極的にその新規名称を使用いただける予定の事業会社の方々と一緒に呼びかけていくことが必要であると考えております。特に本分野はBtoCに従事する事業会社が比較的少ないため、複数のBtoC企業と一緒に、BtoBの企業や開発者へ、同一の名称使用を呼びかける必要がございます。そのような呼びかけの連携可能性があれば、ぜひ「今後の取組方針」としてその取り組みを優先して企画・実行に移したいと思います。
食肉の業界の専門家(一般財団法人畜産環境整備機構 副理事長 原田英男様):肉の業界や生産者の方々との関係が深く、何らかの形でお役に立てればと思っている。現役時代には、今では古い話になるが、クローン牛肉やセシウム牛肉といった事件性のある案件をいくつか担当した経験がある。そういった経験も踏まえて考えると、名称については「細胞性」が一番落ち着くのではないかと感じている。表現としても「突っ込まれにくい」という意味で、「細胞性」が最も適していると思う。家内にも感想を聞いてみたが、「培養」という言葉には不自然さを感じるという意見があった。自宅ではさまざまな話を共有しているが、その中でも「培養」という表現に対してはネガティブな反応があった。国際的なハーモナイゼーションを考えると、「細胞性」に合わせて、英語では「セルベース」という表現を用いるのが適切ではないかと思う。ただし、最初は漢字、つまり日本語で説明した方が受け入れられやすいという感覚もあるため、使い分けをしながら進めていくのがよいと考えている。現在のこの時点での名称は、たとえば今日ここに集まっているメンバーやWT事務局などが、「ひとまずこの名称で共通認識を持ちましょう」といった議論の入り口としての仮決定でよいのではないかと思う。その名称が、メディアや消費者に広がっていく過程で自然に浸透していけば、無理のないかたちで定着していくのではないかと感じている。その上で、認証制度やその他の制度設計も必要となるが、まずは言葉の統一性と、それに対する理解・共感が得られた上で、技術的な認証や基準づくりに進んでいくのが望ましいと考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
クローン牛肉やセシウム牛肉といった案件への対応のご経験を踏まえてコメントをいただきました。英語名称に関しては、実務的には目指す市場で一般的に使用されているものに合わせる形に、少なくとも事業者レベルではなると考えられます。一旦は日本語の名称を「漢字の名称」と、その「読み方としての英語のカタカナ名称」で議論するという方針があり得ると考えております。
また、いただいたコメントを踏まえて、先のリリースでは「製品の上市が行われていない現時点において、企業や研究者による自主的な社会での認知促進・理解形成のための名称の整備を目的」とする点を含めました。
消費者団体関係者:私は消費者団体という立場から話をさせていただく。これまでも遺伝子組換え食品やゲノム編集食品などのリスクコミュニケーションを継続的に行ってきた。リスクコミュニケーションを行う上で、名称は非常に重要であると常々考えている。遺伝子組換え食品もゲノム編集食品も、もう少し早い段階で名称の検討がきちんとなされていれば、ここまでネガティブな印象を持たれることはなかったのではないかというのは、関係者の多くが指摘している点である。たとえばゲノム編集食品については、「培養」の「バ」という文字に違和感があるという話もあったが、それに加えて、私がある県庁主催でゲノム編集技術のリスクコミュニケーションに参加したときの例を挙げたい。そこでは研究者と厚生労働省、消費者省の担当者が参加した。そこで行政の担当者が、「ゲノム編集の“ゲ”という濁音が、“ゴジラ”のような異質なもののイメージと重なってネガティブに捉えられる」と述べていた。この発言を聞き、名称がもたらす印象の強さを改めて認識した。本題に入ると、私は「細胞性食品」が良いのではないかと考えている。「培養」という語には前述の理由のほかに、昨年度の事件の影響もある。昨年、培養によって未知の成分が生成されたとして大きな騒ぎとなった。具体的には、アオカビと紅麹が共培養され、プベルル酸等の物質が作られて健康被害を引き起こしたが、それによって培養の食品に対して不信感を持った人も多かった。結果として、「培養」という言葉に対するネガティブな印象が一層強まったと感じている。このような背景から、「細胞性」という表現の方が適していると思う。また、「細胞性食品」とすれば、国際的に用いられている「セルベースト(cell-based)」とそのまま対応させることができる点も長所である。短所としては、「すべての食品は細胞からできているのだから、“細胞性食品”というのはおかしいのではないか」という意見が出る可能性がある。これは遺伝子組換えの際にも「すべての食品は(組換えではないにせよ)DNAでできているのだから」という指摘があったのと同様である。したがって、「細胞性食品」と呼ぶと、科学的な立場からは「何を言っているのか」と思われる懸念もあるが、そこはリスクコミュニケーションが求められるところだと思う。消費者の反応という観点では、「培養」という語が含まれない方が印象が良いという意見が多いと感じている。また、改めて強調したいのは、名称は非常に重要であるという点である。今後については、表示に関する議論も出てくるだろう。表示の場面では、食品表示基準で名称等が定義付けられて表示制度がつくられる。細胞性食品がきちんと定義づけられ、名称が統一されていることが望ましい。「表に“細胞性食品”などと書いて、裏面の一括表示に異なる名称が書かれている」ような状態は、できれば避けた方がよい。
また、原材料名については、「一般的な名称」でなければならない。したがって、「細胞性食肉」や「細胞性」といった用語で、できるだけ早い段階で統一を進めるべきと考えている。
現在、表示制度の所管は消費者庁であり、食品衛生基準行政も消費者庁に移っている。かつては所管官庁がで分かれていたため調整が困難だったが、今は表示も基準も消費者庁が所管している。そのため、早い段階で名称に関する調整を行うことが極めて重要であると考えている。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
昨年の事件について例を挙げていただきました。細胞性食品とは別分野の事件ではあり、また系は異なるものの、一方で「培養」という同じ技術用語が使われているため、消費者コミュニケーションを行ううえで、昨年の事件と本分野の議論が混同されないよう細心の注意が必要であると考えられます。
また、上記コメントの、遺伝子組換え食品の名称に関連した指摘も、おっしゃる通りです。
加えて、「『表に“細胞性食品”などと書いて、裏面に違う名称が書かれている』状態は、できれば避けた方がよい。」という点もその通りであり、実際に本名称の使用・普及に賛同いただける事業会社と共に、「細胞性」という名称の一層の普及を図りたいと思います。
ジャーナリスト1:以前は日経BP社などで、食の安全に関する記事を執筆してきた。遺伝子組換え食品や食品添加物といった、消費者に誤解されやすいテーマについて、どうすれば正しく伝えられるかという問題に取り組んできた。今回の議論にあたり、メディアの観点から様々な記事を見たところ、一般消費者が目にするメディアにおいて最も登場頻度が高いのは「培養肉」である。これは肌感覚でもある。私自身も数年前から細胞性食品(CF)に関する取材を始めているが、記者でありながら、それ以前は「培養肉」と捉えており、「細胞性食品」という表現があることは、そのとき初めて知った。ましてや、一般の人々の間では「細胞性食品」という言葉は現時点でほとんど認知されていない。専門誌や一部の科学者が集まる論文などでは頻繁に使用されているが、一般メディアの記事においては登場しない。そのため、「培養肉」という言葉が使われ続け、すでに定着しつつあるのが現状である。したがって、今回のように名称について議論を行うことは非常に意義深いと考えている。この3つの候補の中でどれがよいかについては、「培養肉」は認知度が最も高いものの、ネガティブなイメージが指摘されている。これを機に、新たな名称を導入し、業界全体で広めていくことが望ましいと考える。その意味で、「細胞性食品」が適切ではないかと思う。ただし、「細胞性」という表現は、一般の人々にとってはやや科学的・専門的に聞こえ、距離感を与える可能性がある。その点で、「セルベース(cell-based)」というカタカナ表記は、国際的な整合性があり、さらにiPS細胞のように“未来感”“明るいイメージ”を与える語として育てる可能性がある。これはよい機会になると考える。今後の着地点について述べると、遺伝子組換え食品や食品添加物が強いバッシングを受け、それによって多くの事業者が苦労してきた。その苦い経験を繰り返さないためにも、今回はカジュアルな言い回しであっても、研究開発段階で「こう呼びましょう」と合意するだけでなく、これを機に流通や消費者にも周知すべく、ルール化・規制化に向けた動きを加速させるべきである。さもないと、かつて「遺伝子組換えでない」「無添加」といった、優良誤認を招く表示が氾濫し、消費者が遺伝子組換え食品や食品添加物は健康を害すると誤解したように、今回もその二の舞となる可能性がある。「培養」という言葉に悪い印象があるなら、「これは培養していません」といった表示が現れる恐れがあり、それによって消費者の誤解が進み、せっかくの新技術に対する拒否感が強まる危険性がある。したがって、名称が決定したあとも、それに留まらず、制度化・表示基準の整備を進めるべきであると考える。遺伝子組換え食品や食品添加物も、表示ルールが強化された後は、誤解を生む表示は減少している。過去にクローン牛の取材をした際、研究者が「クローン牛は組み換えていないから安全です。そう書いてください」と冗談交じりに言っていたことがある。このように、新しい技術に対して拒否感を持つ消費者心理をどう扱うかが、極めて重要である。名称を早い段階で決定し、ルール化を進め、関係者だけでなく消費者にも広く浸透させることが必要であると強く思う。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
おっしゃる通り、よりオフィシャルな名称と略称を両方セットで推進することについての重要性が非常に大きいと考えられます。今回、漢字表記での「細胞性」について先んじて議論の発表を行ってまいりましたが、略称に関しても早急な議論の深化が必要との理解です。
また、「培養肉」という用語が浸透している中で、どのように名称をシフトしていけるか、そのための産学連携という点についても可能性を模索したいと思います。
ジャーナリスト2:私は三〜四年前からこの業界を取材している。率直な感想としては、三年前に「細胞性食品」という言葉を業界として使っていくという話が出た際、取材をしており、その決定に従って以後すべての記事で「細胞性食品」という言葉を用いてきた。その際には、かなり議論の上で決まった名称だと認識していたため、今になって再びこの言葉の定義を見直すという展開には正直面食らっている。ただ、皆様も望んでこの状況になっているわけではないと理解しており、そのご苦労も察している。取材者としての立場から申し上げると、名称は業界側が決めるものであり、我々は決まったものを使用する。それ以上でも以下でもない。ただし、それがあまりにも頻繁に変更されると困るというのが、メディア側の第三者的な立場である。また取材の中で感じた個人的な意見も述べる。まず、細胞性・培養・細胞培養といった言葉の長短についてだが、「培養」という単語は避けられないと考えている。これまで「細胞性食品」という言葉を使ってきたが、読者の多くはこの言葉だけでは内容を理解しないため、必ず説明文が必要となる。「〜である細胞性食品」と表現する際、結局「細胞を培養して作られた食品」という説明が必要となり、その中に「培養」という語が自然と出てくる。そのため、イメージが悪いからといってこの語を完全に避けるのは現実的ではない。一方、昨日事務局からいただいた資料を拝見し、印象に残ったのは「製法は消費者にとって重要ではない」という指摘である。どのような製法であっても、それによって得られる価値や特徴を名称に反映させることが消費者にとって親切であるという考えは、上記のコメントと相反するものの確かに納得できる。ただし、三年前のWT事務局の提言に立ち返ると、「クリーンミート」や「環境に良い」など、従来の畜産品を否定するような命名は避けるべきという方針が示されていた。これも合理的だと感じていたため、「何が良いか」を明示するのもまた難しい側面がある。さらに、現在考えていることが二点ある。一つ目は、「培養」や「ゲノム」の語感がネガティブだという意見について、個人的にはその感覚に共感はしないが、開発者側がそのような生理的反感を持つ層にまで強くリーチすべきなのかという点である。たとえば、ゲノム編集食品の業界関係者は「どうしても受け入れられない人々は仕方ない」とし、賛成派と中立層に広がっていけば良いという立場を取っていると認識している。このあたりのスタンスを業界としてどう設定するかが問われる。二つ目は、小売事業者の方が先ほど言及した「プラントベース」「アニマルベース」「セルベース」という三分類が国際的にも通用しやすく、合理的なものであるという意見についてである。その通りだと思いつつ、仮に将来、「セル」という言葉自体にも消費者が心理的抵抗を感じるようになる可能性をどう考えるか、という点も気になっている。もしそうなった場合、カタカナ表記であるがゆえに、ネガティブな印象に転じやすいリスクもあるのではないかと考えている。現在「セル」は濁音を含まないため問題ないという判断かもしれないが、今後の展開として留意しておく必要があるのではないかと感じている。明確な結論を出せるわけではないが、以上が現時点での意見である。
[※追ってのメールでのやり取りで、補足の説明をいただきました。]
セルという言葉そのものに具体的な懸念が現在あるということではないが、ゲノムも培養も拒否感をもたれたのは予想外だったと思う。セルという言葉にも予想も付かないような理由で拒否感を示すひとは出て来うるのではないか、という意図だった。ひいてはそういうのをいちいち気にすることはきりがないのではないか、という意図もある。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
「細胞性食品」がもともと候補名となった背景について説明いたします。もともとフードテック官民協議会細胞農業WT(事務局:細胞農業研究会)内の名称決定分科会にて、細胞を培養する工程を経た食品の表示に関する印象調査を実施した結果、「細胞性食品(cell-based food)」、「細胞農業食品(cell-ag food)」、「カルチャード食品(cultured food)」の3つが候補として提案されました。当時の調査は、日本の培地や細胞性食品の開発スタートアップを含む計6社からの協賛によって2021年9月に実施され、名称決定分科会の運営・議論進行は協力先の特定非営利活動法人日本細胞農業協会が担いました。またアカデミアからのアドバイスを受ける形で検討がなされました。上記の3つの名称候補のうち、当時のフードテック官民協議会における農林水産省側より、FAOが当時採用を発表したcell-basedに合わせて「細胞性」でどうかというお話もあり、当時の細胞農業WTでもその名称に合わせるという結果に落ち着きました。上述の経緯から、当時の事務局を務めた細胞農業研究会(((一社))細胞農業研究機構の前身組織)が2022年に関係省庁宛に提出を行った提言書においても、同様の名称が採用されました。また、こういった産学からの呼びかけに対応いただいた結果か、農林水産省、経済産業省、内閣府や過去の首相による国会答弁でも同様の名称を使用いただきました。
一方で、なぜこのタイミングで本名称会議を行うに至ったかというと、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会にて、仮称扱いではあるものの、細胞培養食品という別名称が使用され、一部の企業が対外発信における名称を変更するなど、使用される名称の数が増えたことが要因としてございます。上記部会では食品安全行政のための枠組み検討が主眼であり、またその部会で行われる議論も枠組み内で使用される名称についての議論との理解であり、業界にて使用する言葉と必ずしも同一である必要はない理解です。しかし、当該部会での議論が今後の販売の可能性に直結しているという観点などから、部会に合わせて用語を変更する事例が出てきたという理解です。また、本分野に関与する事業者の数も、2021年に調査を実施した当時よりも格段に増えたことから、改めて名称選定については消費者調査を実施の上、業界内での議論が必要であるとの結論に至りました。
「産学内での名称統一の働きかけ」について、多くの方が必要性を認めながらも、自ら担うのは難しいと感じておられるとの理解です。実際に取りまとめを担うことは容易ではないからです。一つの名称を推奨するにあたっては、その活動に賛同してくださる方々と、別の考えを持つ方々の双方に十分な配慮が求められます。加えて、関係省庁の担当窓口が異動することで、積み上げてきた合意形成を改めて確認する必要が生じる場合もあります。さらに、名称の議論を技術者だけでなく幅広いステークホルダーの意見を取り入れて進めることにも難しさがあります。立場によって「正しさ」「誠実さ」が異なるためです。加えて、議論を個々人の想像にとどめず、実際の消費者の反応を客観的かつ定量的に把握し、それに基づいた議論を行うためには、消費者調査の実施が欠かせません。そこには多くの人的・資金的な工夫と支えが必要です。これまで、NEDOからの間接的なご支援や、細胞農業WTの会員および外部有識者の皆様のご協力を得ながら、WT事務局として主体的に推奨名称の発信を進めてまいりました。今後は、その名称をさらに広めてゆくことを目指します。そのために、消費者コミュニケーションを重視する企業や研究者の皆様と一層踏み込んだ連携を図り、共に情報発信を強化していきたいと考えています。そして、具体的な発信事例を積み重ねていくことが重要です。
Good Food Institute Japan (代表 洪貴美子氏、代替たんぱく推進派国際NPO) :2020年頃からインテグリカルチャー社に関与しており、当時「細胞性」「培養」「細胞培養」という名称案の検討を、同社の社員として担当していた。それ以前は、テクノロジー寄りの技術を用いて消耗材や耐久性品を市場に出す事業会社に在籍しており、マーケットイン志向を強く持っている。現在は、代替タンパク質、CFを含む代替タンパク質産業をグローバルに創出する支援を行うNPOの立場から、海外における取り組みも含めて意見を共有したい。まず、「細胞性」「培養」「細胞培養」の長短についてであるが、今回の議論は、食品企業の方々が指摘するような「利便表示」、すなわち消費者に受け入れられる愛称を定める議論であると捉えている。この三つの名称案については、当時、パッケージ裏に記載する一般名称を検討する目的で案を出し、消費者調査を実施したという記憶がある。従って、今回のように愛称としての検討を行う場合には、この三つはいずれも適さないのではないかと考える。理由としては、マーケットイン志向の立場から、消費者に「購入」という行動変容を促せるかどうかが極めて重要であるためである。したがって、名称については改めて選定し直す必要がある。ただし、パッケージ裏の一般名称として選ぶ場合には、当時選定されたとおり、「細胞性」が最も適していると考える。
次に、名称選定の軸として私およびGFIが最も重視しているのは、「消費者の反応」である。それと同時に、「技術的に正確かどうか」も重要な判断軸と捉えている。この観点から、我々は2019年から英語圏のマーケティング会社などとも連携し、調査と定点観測を行ってきた。GFIとしてはグローバルに「Cultivated Meat(カルチベーテッド・ミート)」を推奨しており、WT事務局を務める団体ともMOUを締結している。「カタカナのセルベースが良いのではないか」という意見もあったが、英語圏において“cell-based”は科学的な印象が強く、日本人にとっての「培養」に近い拒否感を伴うという調査結果があった。そのため、我々は“cultivated”という、より自然や農業、食文化といったポジティブなイメージを想起させる言葉での普及を進めている。欧米やアジア(特に中国)でも、消費者調査と定点観測を継続しており、一度決定した名称を定着させるには、継続的な努力が必要である。2019年から2025年までの過程において、「cultivated」という名称の使用機会は欧州でも着実に増加している。今後も英語圏においては、この名称の定着に向けて努力を重ねていく方針である。一方、日本においては、漢字ベースの愛称が望ましいと考えている。メディアが記事を書く際に、見出し等で文字数制限があるため、短く、端的に伝わる名称であることが事業会社にとっては死活問題である。そうした点を踏まえ、消費者に愛される言葉を改めて検討することが望ましいと考える。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
上記のコメントについて、念のため同団体のスタンスを確認したところ、下記と理解いたしました。
- 和名については「細胞性食品」でよい
- 略称については「セルベース」は避けてほしい。理由はそのカタカナ表記が英語に機械的に翻訳された場合、cell-basedになることが多く、cell-basedは同団体としては今まで消費者受容の低さを背景に避けてきた名称であるためである
- 日本から英語圏への発信の際はcultivated foodを採用してほしい
今回は日本語圏での名称についての議論であるため、英語での名称についてはあくまでも参考という扱いです。また直訳で鑑みると、cultivatedは和訳・直訳で「栽培」や「養殖」という表現が近いため、(細胞)培養を(cell-)cultivatedの翻訳とするのは「意訳的」であるとの理解です。おそらく直訳では「培養」は「Cultured」のほうが「Cultivated」よりも近いと思います。すなわち、同団体が勧めているcultivatedの直訳の名称「栽培肉」等はそもそも日本語圏では使用されていないという点は考慮すべきであると考えております。機械的な直訳では貴団体の推進されようとしているCultivatedにはつながらないと思われます。ちなみに、細胞性は直訳的には“cellular”が最も近く、”cell-based”は意訳に近いです。
日本語の場合は「細胞性」にご賛同いただいた背景として、おそらくcultivated foodの普及活動が英語圏でしっかりされていれば、細胞性の英訳としてcultivated foodが選ばれる可能性は一定程度あると見込まれたからではないかと考えられます。機械翻訳であっても、プロによる翻訳であっても、足元の訳語はぶれるものの、英語圏での普及活動がうまくいっていれば、やがては翻訳のブレが解消されていくはずであると、編者の個人的な意見としても感じます。
漢字では上述のことが言える場合、現時点で日本語の俗称候補である「セルベース」が国際世論にどれほどの影響を与えるかについては、もう少し議論が必要かもしれないと感じました。本件につきましては継続的な議論が必要との理解です。
「セルベース」につきましては、誤認回避の効果については未検証であるため、先のリリースから「細胞性」と同様の扱いで「セルベース」を提案することは削除をいたしました。ただし、先のリリースの中で、議論の過程で出た意見として記載されている箇所については、議論の透明性や中立性の観点から「セルベース」という名称候補を残したいと思います。
食品安全の研究者(東京農業大学 食品安全研究センター 五十君 静信センター長):まず一つには、名称をつける時にどういう観点でつけるかという点について。技術を中心とした形で、例えばGM・ジェネティカリーモディファイドという技術を用いたものという名称での表現は、科学的にはわかりやすいというメリットがあります。従来はそのような観点で、使っていたという経緯はあります。一方で、皆さん非常に危惧しているように、消費者のアクセプタビリティの課題です。この観点からしますと、特に日本の場合は、食の分野では自然物に対しては非常に寛容であり許容されるのですが、人工的なものに対してすごく嫌悪感を抱くという傾向が顕著です。社会全体として戦略的にこの開発された食品を今後どうしてくかという観点で見た場合、技術に偏らず、食品としての特性をうまく表現するということで名称を決めていくことが有効であると思われます。そのどちらを選択するかというのが今回の議論の中心なんではないかと思います。この3つの候補は、どれも技術中心の従来の名前のつけ方ではあると思いますが、セルベースは、技術というよりもむしろ性質を表していると思われます。ただどの程度まで厳密性を出しているかという点で違いがあると理解しています。それで、どれを選ぶかについてですが、日本語にした時のニュアンスの問題と、それから日本の消費者のイメージとして、人工物に対する非常に拒否感が強いところ。ここをいかに和らげるようにするかということを考えますと、私は個人的には細胞性あたりがやはり無難かなという風には考えています。
技術でもって厳密に見ていったら細胞培養という形で他と区別するのが適切ではないかと思うのですが、一番心配なのは遺伝子組換えの二の舞になってしまうことです。せっかく有用な技術であるのに、日本がそれを積極的に開発にもっていけない、企業側が非常に躊躇するということになる可能性があるとすると、細胞性という、農林水産省、経済産業省、内閣府等も使っていた細胞性食品という形にだんだん動いていっていたと思っています。
当初は培養肉というような言葉からスタートしたわけなんですけれども、私としましては細胞性というのが一番無難で、セルベーストというWHO/FAOの国際的な流れに沿った訳として選択したという考え方で統一されるのがいいんじゃないかなと思います。このように発言をしていただけると嬉しいと思います。
日本の行政上では遺伝子組換え添加物という表現があります。コーデックスのスタンダードが技術ベースでGMを扱っちゃっているので、製造の段階で遺伝子組換えを使った、「プロダクトとしての添加物」なのにもかかわらず、頭に遺伝子組換え添加物って書いてあるんですね。しかし、食品添加物として見た場合は、これちょっと違和感が出てきます。プロダクトには遺伝子組換え体は含んでいないわけです。だから、製造工程の技術を優先するとこういったことが起こってしまって、その名前が定着てしまった。私がもう20年ほど前からあの遺伝子組換え添加物は頭を取らないと、遺伝子組換え体自身を含まないようなものに対して、遺伝子組換えって頭につけてしまうと消費者は非常に嫌悪感を感じてしまうし、消費者が忌避する根拠になってしまうから考え直すべきだということを伝えてはいるんですが、そのままとなっています。こういったことを考えますと、細胞培養という厳密な技術の言葉を表面に出した時に、例えば単体ではなくて、他の素材として使ったりする時にちょっと足を引っ張る可能性があるのかな?と。初期の遺伝子組換え添加物のようになるような気がします。あくまでも遺伝子組換えでしたら組換え体そのものを食品自体に含むものというような、そういう定義にしておけばよかったと感じます。技術優先で、この技術を使ったものについては厳密にこうつけますみたいになってしまったために起こったあまり良くない例と言えるんではないかと思います。そういった面では細胞性という表現は若干中間的という表現だとありましたけれども、細胞培養のように工程にかかる厳密な言葉を使うよりは若干そういったリスクは下がってくるという気はいたします。
論点としては、技術の新規性のほかに、食品の場合は国際整合性が非常に重要だと思います。国際的なFAO/WHO、コーデックスあたりの使っている用語の中から選択するというのが、やはりいいのではないかなと。それをいかに日本語に置き換えるかの問題。
いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等:
先生のコメントを、先のリリースの「製品特性を重視した表現の適切性」に追記いたしました。特に、「培養」、「細胞培養」、「細胞性」といった名称は、いずれも技術に基づいた名称であるが、中でも「細胞性」は、「培養された細胞を原料として使用した(加工)食品である」という、製品の実態に即した説明に近いという点を整理しました。
また、工程において使用される技術のみにフォーカスを当てた形での名称検討における課題感につきましても共有いただきました。
※「いただいたコメントへの事務局における対応方針、補足等」は、細胞農業WTの事務局長である、(一社)細胞農業研究機構 代表理事 吉富愛望にて執筆されました。
■ お問合せ
https://jaca.jp/contact/