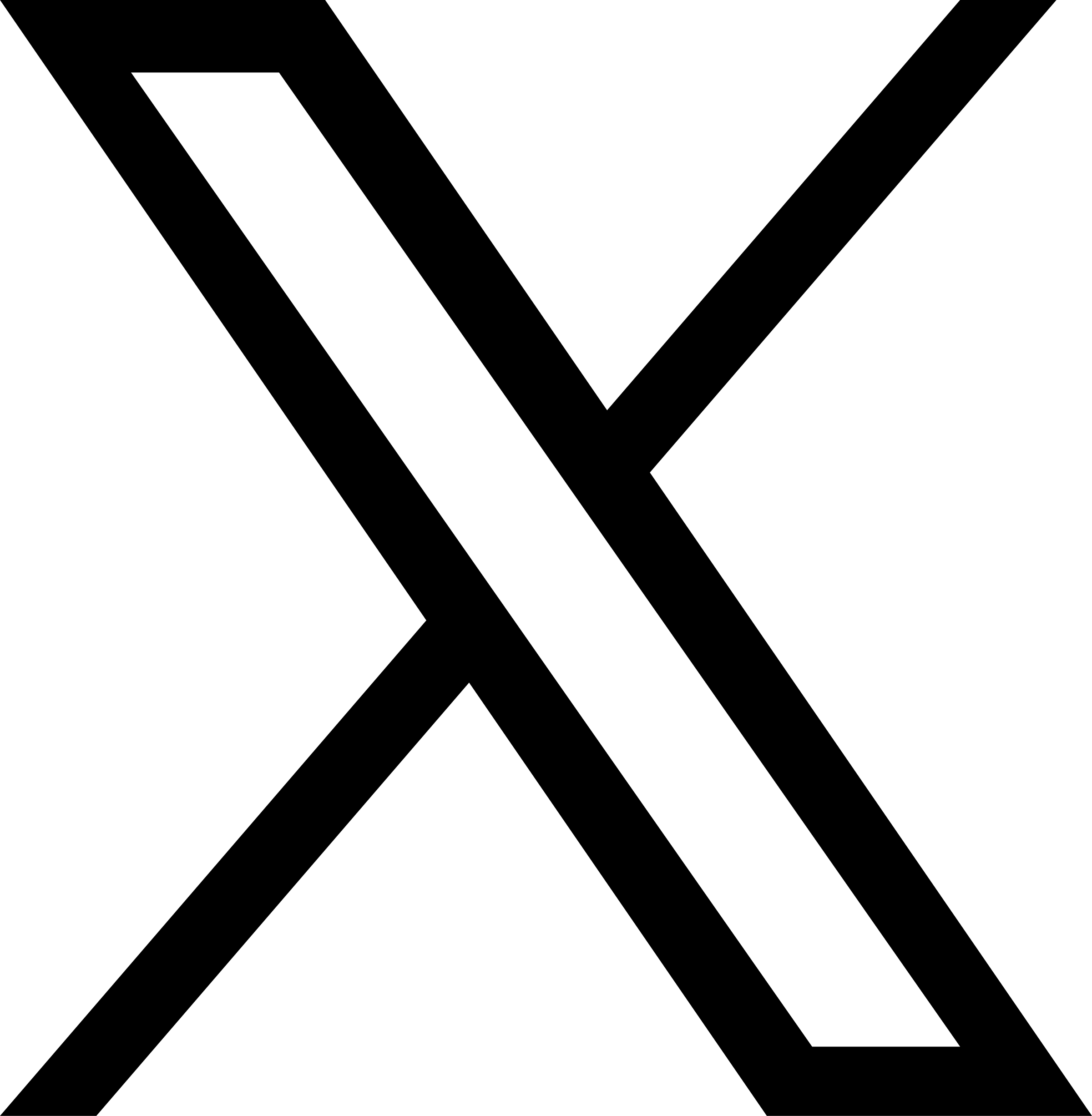「国内における細胞性食品のリスク評価および管理方針に関する考え方(専門家案)」を発表しました
2025年4月28日
ご報告と背景
一般社団法人日本細胞農業研究機構(JACA)は、2025年4月、「細胞性食品のリスク評価および管理方針に関する考え方(専門家案)」を発表いたしました。
正式な内容については、既存の記事をご参照ください。
本案は、過去に作成した業界案([リンク])を基礎に、食品安全性に関わる分野横断的な専門家の知見を取り入れて再構成したものです。日本における今後の制度設計や、製品の安全性検討の土台として広く活用されることを目的としています。
本書の作成において直面した様々な課題
本案の作成は、多くの面で挑戦的な作業となりました。
その主な理由は次の2つに集約されます。
① 極めて分野横断的な議論
一つ目は「細胞性食品」が分野横断的な議論を必要とすることです。
既存分野の安全性に係る議論を組み合わせて、新規の生産方法による食品の安全性を検討しようとする場合には、分野横断的な議論が不可欠です。このような分野横断的な議論を整理するにあたっては、分野ごとに異なる前提や視点の違いに十分配慮する必要がありました。
例えば、分野間の言語の壁(同じ言葉でも別の現象を想起する等)、思考様式の違い(回帰的・予測的のように考え方の順序や着眼点が異なる等)、系の性質の違い(発酵食品分野における知見が応用できる場面もあれば、培養細胞と微生物では増殖速度が異なり、その違いが衛生管理に大きな影響を及ぼす等)、慣習の違い等が整理を難しくする要因として考えられました。
議論の整理にあたって留意した、異なる分野間の「違い」
特に以下のような分野間のギャップが議論の整理を複雑にしました:
- 食品分野と医薬品分野のリスク評価における前提の違い
- 医薬品は摂取量(投与量)が厳密に管理されるのに対し、食品は自由摂取が前提となる
- 医薬品の標的分子は明確であるのに対し、 食品は標的分子を想定していない分、網羅的に漏れなくハザードについての検討が必要
- 再生医療等製品は「非経口(parenteral)の無菌医薬品」、すなわち直接ヒトに注射や移植することを前提とするが、食品は経口摂取を前提とする
- リスクとベネフィットのバランス。医薬品は「治療効果」というベネフィットを設定し、それに対するリスクを評価する。一方、食品は「効果」を設定できない分、リスクの許容度が低くなる
- 動物実験によるリスク評価の有効性の違い
- 成分が明確で高純度な場合の医薬品*などと比較して、食品は複数の成分から構成されるため、その分、実験結果から因果関係を評価することが難しい可能性がある(*再生医療等製品や生薬等の例外はあり得る)
- 生理活性物質に対するリスク評価の場合は、ヒト以外での動物を用いた実験が意味をなさない場合があり、ヒトへの外挿性の担保も難しい
- 実験動物を用いた慢性毒性試験において設定された、毒性学的に安全性が担保できる投与量と比較して、ヒトの1日あたりの想定たんぱく質摂取量ははるかに多く、当該実験の結果のみで安全性を担保することは難しい
- 培養細胞と発酵食品における微生物汚染による生産被害の違い
- 発酵食品には様々な種類があるが、多くの場合、無菌状態で培養しているのではなく、目的菌(乳酸菌や酵母等の有用微生物)による発酵を促しながら、雑菌(意図しない微生物)の増殖を抑えた環境で管理されている。これに対して培養細胞(動植物細胞)は増殖が遅く(世代時間は短いものでも半日以上)、一部の増殖の速い微生物(世代時間は15分以下のものさえある)が混入すれば急速に繁殖し、生産に深刻な影響を及ぼすおそれがある
- in vitro(生体外)とin vivo(生体内)での細胞増殖環境がもたらす影響の違い
- 生体内で細胞が増殖する際、何らかの通常と異なる事象が起きた場合には、それを排除する「自浄作用」が働くことがある。一方で、生体外の培養系では、同様の機構が異なる応答や機能として現れる可能性がある
- 細胞性食品を製造するにあたり、生体外で大量に細胞を増殖させる(大量培養)必要がある。大量培養は生体内と細胞が増殖する環境が大きく違うため、細胞の特徴の変化が生じる可能性がある。細胞の特徴の変化は細胞性食品の品質等に影響を与える可能性があるため、特徴の変化がないことを監視することが重要である
- 医薬品と食品の上市に係る手続きの違い
- 医薬品は上市にあたり厚生労働省からの承認が必要であるが、食品はあらかじめ販売前に安全性確認プロセスかつ承認制度の枠組みがある特定の食品分野(遺伝子組換え食品)を除き、食品製品ごとの承認は行われていない
- 食品分野の場合は、食経験に乏しいとみられる食品や調理工程を経たものであっても、消費する人口や頻度等の規模の大きさ、健康被害の有無によって上市前における産官学間の安全性の見解整理が行われない場合もある
- 細胞性食品分野と医薬品分野における「株化細胞」の意味合いの違い
- 医薬品分野の場合、「株化細胞」と聞くとヒトのがん細胞を想起し、ヒト株化細胞を体内に直接投入する(非経口)と腫瘍となる可能性があると考えられる。一方、細胞性食品分野の場合、「株化細胞」は非ヒトの細胞であり、その動植物細胞にとって最適化された培養環境において高い増殖能を有する細胞(がん細胞ではない)であり、その後経口摂取がなされることを前提とする。よって同じ言葉でも想起される内容が異なっている点に注意して議論を整理すべきである
- 既存の新開発食品の安全性審査の考え方との違い
- 日本では遺伝子組換え食品やゲノム編集食品等、新開発食品を上市するための審査制度や届出制度が存在する。しかし、これら制度は組換え遺伝子に由来する新規のタンパク質やゲノム編集で欠失した遺伝子による変化に着目するものであり、そのまま活用できる評価方法もあれば、そうでないものもある
このように、「言語」「思考様式」「制度」「慣習」等、多岐にわたる分野間での違いを乗り越えて議論を統合することが必要でした。
議論において重視した姿勢
本案では、次のような姿勢を重視しました:
- 既存の制度や評価手法をむやみに否定せず、活用可能な要素を適切に組み合わせる
- 専門用語の使用にあたっては、分野ごとに異なる意味が想起される可能性に配慮し、用語の定義を明確化する
- リスク評価とリスク管理を分けて整理し、製品の種類や使用環境に応じて柔軟に適用可能な構成とする
このように、単一分野の理論に依存するのではなく、実務性と柔軟性を兼ね備えた「現場で活用できる指針」となることを目指し、本案を構築しました。
② 具体案までの踏み込みへの困難さ
二つ目は、現時点では製品プロファイルの設定が難しく、本書の内容を詰めるにあたって具体的な管理方針にまで踏み込むことが困難だった点です。
リスク管理とは本来、具体的な製品の製造原料・工程や製品プロファイル(動物種x細胞型x培養方法x食品加工等)が明確になった段階で初めて、「この時点でこのような管理措置を講じること」という要求事項を設定することが可能となるものです。弊機構は細胞性食品の開発企業ではないことや、本分野において、特定の製造原料・工程や製品プロファイルが主流となり得るという予測もまだ難しい状況であったため、具体的に製品プロファイル等を絞っての議論が困難でした。特定の企業の細胞性食品に絞る場合、その企業への情報開示の負担が大きく、協力を得ることが困難であるということが過去のステップIIにて明らかであったため断念しました。一方で動物種x細胞型x培養方法x食品加工等の各組合せに応じたすべての管理事項を設定することや、それぞれの事項について「推奨」なのか「必須」なのかといったレベル感を明示することには工数がかかりすぎるという点で困難でした。
今後のステップ
今後具体的にリスク管理の要点を絞るにあたっては、開発と独立した専門家のみならず、細胞性食品の開発企業も交えた検討が不可欠です。したがって、次のステップVにてレギュラトリーサイエンスの専門家と開発企業間の意見のすり合わせを目指したいと思います。
資料・別紙1~4の閲覧およびダウンロード
※2025年12月15日に資料中の一点誤植を修正いたしました